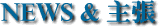
![]()
「解放新聞」(2018.03.12 -2850)
1
死者1万8千人の犠牲者を出した東日本大震災から7年が経過した。被災地では、生活の基本となる住宅再建のための災害公営住宅の建設や集団移転などがすすんでいるが、2018年1月末現在、まだ7万5千人が仮設住宅などで避難生活を続けている。なかでも原発事故によって多くの住民が避難した福島県は、ピーク時からは半減したが、いまも5万1千人が故郷を離れて暮らしている。被災者の苦労は、住宅再建だけではない。被災地では地盤のかさ上げによる商店街や中心街の再建、あるいは病院や介護施設の建設もまだまだ途上だ。ところが、国は「復興費用は全額を国が負担する」という約束を破り、2016年度から被災自治体に一部負担を押しつけるなど、国の被災者支援策、復興策の打ち切り・縮小を強引にすすめている。たとえば、国は当初、被災者の医療費・介護料を全額負担していたが、2012年から国8割、自治体2割に変更し、宮城県は現在、70歳までのひとり暮らしで所得のない人に限定している。
ところで今年、岩手・宮城の両県は、被災者を直撃する新たな問題に直面する。
一つは、2018年度にはじまる災害公営住宅の家賃引き上げだ。国は、低所得世帯にたいして入居から5年間の家賃軽減措置をおこなってきたが、それが段階的に縮小される。今年から2021年にかけて家賃がしだいに値上げされ、2022年には一般の公営住宅と同水準になる。家賃の引き上げ対象は被災3県の入居世帯2万4436世帯(2017年11月末現在)の73%にあたる1万7829世帯だ。復興庁は自治体が独自判断で減免を続けることを認めているが、自治体間で大きな格差が生じている。
また、被災世帯に市町村が最大350万円を貸し付ける災害援護資金の返済が、今年から本格化する。宮城県内の市町村は6年の猶予期間をへて今年から返済事務をはじめるが、今後、借金の返済に追われる世帯が急速に増えていくことが予想される。宮城県内では、32市町村が2万4千人に計約405億円を貸し付けているが、償還額は2017年3月末時点で37億円にとどまる。
時間とともに震災の記憶は風化し、被災者の「自立」が折にふれ、語られるようになった。その陰で、多くの被災者が家賃や返済に追われるという深刻な事態が生まれようとしている。
2
ところで、いまも5万人以上が避難を強いられている福島県では、経済的な負担だけでなく、故郷の喪失という事態が想像以上に人びとに大きな精神的ダメージを与えており、震災後の持病の悪化や自死、孤独死などの原発事故関連死が2115人と大震災による直接死の1・3倍になるなど、深刻な状態が続いている。安倍首相は、事故をおこした福島第1原発の廃炉に向けた収束作業は「完全にコントロールされている」といっているが、溶け落ちた核燃料の位置や状態がいまだ把握できず、あまりの高線量に調査さえ難航している。放射能汚染水対策として350億円を投じた「凍土遮水壁」も十分な効果をあげず、破壊された原子炉建屋や核燃料から溶け出した放射性物質をふくむ汚染水は100万トンをこえて、現在も毎日増え続けている。
それにもかかわらず安倍首相は、原発再稼働と原発輸出という原発推進政策をすすめている。安倍首相は、将来にわたって原発を維持するとした「エネルギー基本計画」(2014年4月)に続き、2015年7月には、2030年度の電力需要の20〜22%を原発で賄うとした「長期エネルギー需給見通し」を決定した。そして、そのため「30基台半ばの原発」が必要だと叫び、原子力規制委員会が定めた「新基準」をテコに、東京電力・柏崎刈羽原発をふくめ大半の原発を再稼働させようとしている。しかし、「新基準」は、火山学者が無理だと指摘しているのに巨大噴火を予知できると強弁するなど、きわめてずさんなものだ。
また安倍首相は、国内の再稼働で日本の原発の「安全性」を装い、原発メーカーと連れ立ってトルコやインドへ原発輸出の「トップセールス」に奔走している。
日本は、大震災のあとの2年間「原発ゼロ」を経験したが、原発なしでも電力不足にはならなかった。また節電や再生可能エネルギーの導入がすすんだ結果、「原発ゼロ」の2014年度以降、二酸化炭素排出量は減っている。日本社会は原発なしでも十分やっていけるのだ。原発の再稼働にたいしては、司法も福井地裁が大飯原発(関西電力)の運転差し止めを命じ(2014年5月。高裁係争中)、伊方原発も再稼働直後に広島高裁の仮処分決定により運転を停止した(2017年12月)。いま日本は、原発を再稼働させ原発依存社会を続けるのか、再稼働を許さず「原発ゼロの日本」にすすむのか、大きな分岐点に立っている。
3
2017年4月、政府は「除染で放射線量が低下した」として、5市町村の一部にかかる帰還困難区域と大熊・双葉両町全域を除く、大部分の避難指示を解除した。解除から1年が経過する浪江町・富岡町の帰還者は約2%、飯舘村の帰還者は1割程度にとどまる。ほとんどの人は、7年のあいだに仕事や学校など避難先での生活が定着し、故郷には戻らない。被災者が帰還をためらうのも無理はない。除染後も被災地の放射線量が十分に下がらず、空間線量が毎時1マイクロシーベルトを上回る高線量地域も多い。集落の目の前に除染廃棄物のフレコンバッグが山積みにされ、無人の家は荒れ放題で、ネズミ、ハクビシン、タヌキ、アライグマ、イノシシなど野生動物が侵入し、とても住める状態ではない。
ところが国は被災地の現状を尻目に、避難指示解除からおおむね1年後を目処に避難者への補償の打ち切りをおこなう方針を打ち出し、避難指示区域外から避難している「自主避難者」については、すでに2017年3月末で住宅無償提供を打ち切っている。
昨年10月には大熊町で、12月には双葉町で、放射性セシウム濃度10万ベクレルをこえる廃棄物を貯蔵する中間貯蔵施設への搬入がはじまった。福島県内の除染廃棄物は約2200万立方㍍にのぼる。今後30年以内に県外に搬出して最終処分する予定だが、最終処分場の目処が立たないなかでの見切り発車に、住民は「中間施設だといっても最終処分場がなければ、そこが最終処分場になるのは見えすいている。最終処分場を被災地に押し付けるのか」と強く反対している。
住民の心配は、たんなる思い過ごしではない。2017年12月25日に公表された最新の福島県民調査報告書によると、福島県の小児甲状腺がんとその疑いの子どもたちは、合計193人にのぼる。福島県は甲状腺がんを、「悪性ないし悪性の疑い」という言葉を使い、あたかも甲状腺がんでない子どもたちもふくまれているように書くことで焦点をぼかしているが、手術を終えた160人中、良性結節だったのはたった1人にすぎず、99%は小児甲状腺がんであった。
4
昨年の衆院選で「原発ゼロ基本法」の制定を公約に掲げた立憲民主党は、東日本大震災から7年となる3月11日までに法案提出を計画している。法案では2030年までの全発電用原子炉廃止を政府目標とし、廃炉の支援、原発立地地域の雇用創出に国が責任をもつことなどが盛り込まれる。原則40年とする運転期間の延長や新増設も認めない。国会は、これを叩き台にして本格的に原発再稼働問題を議論するべきだ。国民も政治家や専門家に任せず、未来を担う子どもたちのために原発をどうするべきか真剣に考えるべきだ。
福島県では、いまも5万人をこす避難者がいる。廃炉の見通しさえ立たない現実をみれば、一日でも早く「原発ゼロの日」を迎えたいというのが国民の願いだと思う。再生可能エネルギーに転換し、原発に依存しない社会を実現するという政策は、世界の潮流である。

「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 210円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)