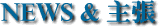
![]()
「解放新聞」(2025.01.25-3126)
狭山事件再審弁護団は、昨年8月の三者協議での確認を受けて、分析化学の専門家であるL名誉教授に依頼し、東京高等検察庁で、ハンドヘルド型蛍光X線分析装置を用いて、インク資料の元素の計測をおこなった。その結果をまとめた鑑定書を昨年12月20日、東京高裁第4刑事部に提出した。
今回のインク新鑑定(L鑑定)の結論は、2018年に提出されたI教授による鑑定と同じく、被害者が事件当日に書いたペン習字浄書の文字からはクロム元素が検出され、発見万年筆で書いた「数字」からはクロム元素が検出されないというものだ。この鑑定の結論から、ペン習字浄書と発見万年筆で書いた「数字」は、異なるインクによって書かれたものということになる。
そして、このことは、発見万年筆は被害者の使っていた万年筆ではないという合理的な疑問を強めることになる。
蛍光X線分析は科学的な分析手法として、一般的に承認され、今回使われた装置は、さまざまな用途で実際に使われている装置で、分析をおこなったL鑑定人らは、この機器を使用する分析技術を習得した専門家である。鑑定結果が科学的に高い信用性をもつことは明らかだ。
また、今回のL鑑定では、別の専門家(I教授)が別の蛍光X線分析装置を使って調べたのと同様、発見万年筆で書いた数字のインクからクロム元素が検出されなかったのである。発見万年筆のインクとペン習字浄書のインクが異なるという事実の客観性、科学性は、もはや動かし難いと言うべきであろう。
万年筆については、2度の家宅捜索後に発見されたという経過の疑問についても、弁護団は心理学者による探索実験にもとづく鑑定書を提出している。そもそも、ふだん使うこともない万年筆を自宅に持ち帰って勝手口の鴨居(カモイ)の上に置いていたという自白じたいの不自然さもある。
これらの証拠とインク鑑定の結果を総合的にみれば、自白したとおりに被害者の万年筆が石川さんの家から発見された、として有罪の決め手の一つとした狭山事件の確定判決に合理的疑いが生じていることは明らかだ。
弁護団は鑑定書提出とあわせて、L鑑定人の証人尋問を請求した。今後は、インク新鑑定を含めた鑑定人の証人尋問の実施が焦点だ。東京高裁が鑑定人の証人尋問をおこない、再審を開始するよう強く求めたい。
年明けの1月14日に63回目の三者協議がひらかれた。
弁護団は三者協議に先立って、証人尋問の実施を早期に決定してほしいと求める意見書を裁判所に提出し、協議の場でも証人尋問のすみやかな実施を求めた。
一方、検察官は、L鑑定にたいして今後、意見書を提出すること、証人尋問については従来どおり反対であるとのべた。
次回の三者協議は3月上旬にひらかれる。弁護団が求める証人尋問の採否はまだ決まっていない。鑑定人の証人尋問・再審開始実現に向けて、重要な局面である。東京高裁第4刑事部(家令和典・裁判長)が、筆跡やインク鑑定を含めた鑑定人の証人尋問をおこなうよう世論をいっそう拡大するとりくみが必要だ。証人尋問を求める署名活動を全国各地で強化していこう。
狭山事件の再審を求める市民の会事務局長の鎌田慧さんらは、2月はじめに東京高裁に署名を提出し、要請行動をおこなう。
石川一雄さんは年明けに86歳になった。証人尋問をおこない、なんとしても再審を開始してほしいと訴えている。61年以上もえん罪を叫び続ける石川さんの無実と狭山事件の再審を訴え、証人尋問を求める署名をさらに拡大し、東京高裁第4刑事部に届けよう。
昨年、再審無罪判決が出された袴田事件では、2014年に静岡地裁で再審開始決定が出されたにもかかわらず、再審開始が確定するまでに9年、再審無罪判決まで10年も費やし、袴田さんがえん罪を訴えて58年もの時間がかかった。
再審開始の決め手となった「5点の衣類」のカラー写真が検察官から証拠開示されたのは、事件から44年以上も経った10年12月だった。最初の再審請求(1981年)から29年以上も経ってからの証拠開示だったのだ。検察官が最初の再審請求で証拠開示していれば再審開始はもっと早かったはずだ。また、検察官の再審開始決定にたいする不服申し立てがなければ、10年前に再審公判が始まり無罪判決が出されていたはずだ。
検察官が証拠開示に応じず、一方で裁判所の再審開始決定に不服申し立てをおこなうからこそ、えん罪犠牲者は長い闘いを不当に強いられているのである。
狭山事件でも、逮捕当日の上申書や取調べ録音テープが証拠開示されたのは10年5月、事件発生から47年後、最初の再審請求から43年後である。この間ずっと、弁護団の証拠開示請求に応じず、求める証拠があるかどうかも答える必要がないなどと不当な対応に終始している。
石川さんは現在86歳。袴田さんと同じように検察官の不服申し立てによって再審開始が確定するまでに9年もかかったとしたら、石川さんは95歳になってしまうのだ。
こうしたえん罪犠牲者の闘いが長期にわたる原因となっている現行の再審手続きの不備を法改正すべきとの声が、えん罪被害者、弁護士、学者、えん罪事件支援者から大きくなっており、袴田事件の再審開始を機に大きく動いている。
日本弁護士連合会は、再審請求における検察官の証拠開示の義務化、再審開始決定にたいする検察官の不服申し立ての禁止、裁判所による事実調べなど、手続きの整備の規定を盛り込んだ「刑事訴訟法」等の改正案(「再審法」改正案)を23年2月に公表し、国会での審議を求めた。
これを受けて、24年3月には、各党の党首らがよびかけ人となって、超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が結成され、会長には柴山昌彦・衆議院議員(自民党)、幹事長には逢坂誠二・衆議院議員(立憲民主党)、事務局長には井出庸生・衆議院議員(自民党)が就任、現在、363人の国会議員が参加するにいたっている。
また、19道府県議会を含む500以上の地方議会で、「再審法」改正を国会に求める意見書が採択されている。(いずれも2025年1月時点)
議員連盟に参加する議員は全国会議員の過半数となっており、通常国会で議員立法として「再審法」改正法案の提出、可決成立が実現可能な状況になっている。
「再審法」改正を求める声が大きく広がるなかで、昨年12月20日に法務省は法制審議会に「再審法」改正を諮問するという方針を打ち出してきている。そもそも、検察庁、法務省は「再審法」改正の必要はないとして、反対してきた。法制審は、そうした法務省が事務局となって人選、議事進行をおこなうものであり、改正議論が先延ばしになり、内容も法務・検察の思うままになる危惧をもたざるを得ない。明らかに議員立法つぶしの動きと言わざるを得ない。私たちは、「議員立法による早期の再審法改正」を求めていく必要がある。
1月24日からの通常国会は大きなヤマ場である。私たちも、地元の国会議員、議連への参加の働きかけと要請をすすめよう。「再審法」改正を国会に求める請願署名を集めるとともに、地方議会での意見書採択の運動、首長の賛同表明などのとりくみをすすめよう。
石川さんの再審無罪を一日でも早く実現するうえでも、「再審法」改正は緊急の課題だ。狭山再審実現とあわせて、「再審法」改正に全力でとりくもう。
※狭山事件の再審請求において証人尋問を東京高裁に求める署名用紙、「再審法」改正を求める国会請願署名は、いずれも部落解放同盟中央本部のホームページでダウンロードできます。
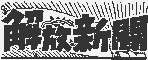
「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)