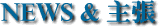
![]()
「解放新聞」(2025.04.25-3136)
今年は、戦後80年、1975年に「国際女性デー」が国連で制定されて50年、また、55年におこなわれた第4回世界女性会議(北京会議)で「北京宣言と行動綱領」が採択されて30年を迎える。さらに、3月8日の「国際女性デー」は、女性の権利向上とジェンダー平等を推進する象徴的な日となり、「北京宣言と行動綱領」にある12の重要課題を掲げ、各国のとりくみの指針になっている。
「世界経済フォーラム」が毎年発表している「ジェンダーギャップ(男女平等)」指数(2024年)の日本の順位は、146か国中118位だった。前年(125位)に比べて少し上がったが、女性管理職の比率は低く、国会議員全体(衆議院議員・参議院議員)に占める女性議員の比率は、19・0%(24年11月現在)と、いぜんとして少ない状況で世界的にみても低水準だ。
日本の人口は年々減少し、少子高齢化社会を迎えている。24年5月に「育児・介護休業法」の改正案が国会で可決・成立し、今年4月と10月に施行される。改正内容は、子育て中の柔軟な働き方の拡充や、男性の育児休暇の取得状況の公表をはじめ、100人を超えるすべての企業に取得状況の公表を義務づけることや、介護が必要になった従業員への支援制度などが盛り込まれている。今後も男女がともに働き続け、仕事(ワーク)と生活(ライフ)の両立が可能となるような社会の実現をめざすためには、働きやすい環境整備をはじめ、各種休業制度の充実と待機児童の解消などが重要な課題だ。現在も日本社会には、女性にたいする差別が存在しており、性別による役割分業は当然のようにある。育児や家事、介護などを分担する時間は女性の方が圧倒的に多く、男女の賃金格差、管理職の男女比率、非正規雇用に占める女性の割合など、雇用の分野をはじめ、女性の社会進出における具体的な男女間格差の実態は改善されていない。政府や国会議員が条約や国内法の具体化に真剣にとりくまなければ男女間格差の課題は解決されない。
暴力には、戦争や殺人などの犯罪、家庭内暴力、強制性交、強制わいせつ、DV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者や恋人からの暴力)、子どもへの性的虐待、女性性器切除や戦時下の性暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、尊厳を傷つける言葉の暴力(モラハラ)など多様な形態と背景がある。また、セックスワーカーへの蔑視や、性的マイノリティ(LGBTQ+)への攻撃などジェンダーにたいする暴力も強まっている。暴力は重大な人権侵害であり、許されない行為だ。
これまでも官僚のセクハラ発言や、国会議員による女性や性的マイノリティにたいする差別発言が起こっている。アイヌ女性と在日コリアン女性が2023年に杉田水脈・前衆議院議員の差別発言にたいして、札幌と大阪の法務局に申し立てをおこない、それぞれの法務局から民族差別であるとして「人権侵犯」と認定されたが、本人は反省もなく、居直ったままである。私たちは、今後も包括的な差別禁止法の制定や国内の人権機関の設立に向けとりくんでいかなければならない。さらに、部落差別や女性差別、障害者差別、性的マイノリティなどにたいする差別撤廃に向けた闘いと、複合差別にもしっかりと視点を置いたとりくみが必要だ。
今年、第6次男女共同参画基本計画が策定される。7月には公聴会や意見募集(パブリックコメント)が予定されている。部落女性の声を反映させるために、パブリックコメントにとりくむとともに、今後も、自治体で男女共同参画審議会委員の一般公募があれば積極的に応募し、委員会のなかで部落女性をはじめ、マイノリティ女性の声を反映させていこう。
昨年10月に、スイス・ジュネーブの国連本部で女性差別撤廃委員会による「女性差別撤廃条約」の日本政府審査が8年ぶりにおこなわれた。私たち部落女性は、在日コリアン女性、アイヌ女性とともに三者でNGOレポートを提出し、女性差別撤廃委員に実態を訴えるため、部落女性の代表を2人派遣した。
女性差別撤廃委員会からは、8年前の勧告から進展しない日本政府の姿勢にたいし、厳しい指摘があり、日本における女性の人権状況について懸念と改善のための勧告が再度出された。また、総括所見では、マイノリティ女性などが交差的な形態の差別のために教育、雇用そして健康へのアクセスが制限されているとし、マイノリティ女性たちの人権課題についてとりあげている。今後も、アイヌ女性や在日コリアン女性、部落女性の三者でおこなったアンケート調査結果や、日本政府に出された勧告をふまえ、関係省庁との交渉を継続的にとりくみ、マイノリティ女性にたいする施策の充実を共同で要求するなど、ねばり強く働きかけをしていかなければならない。さらに、03年に続き今回も女性差別撤廃委員会から「選択的夫婦別姓制度」導入の必要性を強く指摘された。24年3月には、日本経済団体連合会(経団連)をはじめ、企業の経営者たちが「選択的夫婦別姓制度」の早期導入を求める要望書と署名を、法務副大臣に手渡した。「選択的夫婦別姓制度」の早期実現を求めるとりくみは大きく広がっている。また、「旧優生保護法」によって強制された不妊手術の問題では、22年2月、大阪高裁が国に賠償を命じる初めての判決を出した。今後も、国家賠償訴訟を支援し、国の責任の明確化と謝罪を求めていこう。ハンセン病家族訴訟でも、19年6月に熊本地裁が国への損害賠償を命じたが、ひき続き、国の差別政策の誤りを明確にしていくために支援を強めていこう。
今日、ロシアによるウクライナ侵略戦争が長期化し、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区での戦闘激化をはじめ、世界各地で軍事衝突が続いており、国際社会での対立や分断がいっそう深まっている。
石破政権は、昨年の衆議院選挙で与党の議席を大幅に減らし、政権維持のために一部野党に譲歩するなど、不安定な国会運営をすすめながらも、これまでの政権同様、軍事大国化と憲法改悪に向けた策動を強めている。この間、日本社会における格差や貧困、差別の問題はより深刻化し、差別排外主義による難民排斥や移住労働者への蔑視、在日コリアンへのヘイトスピーチなど暴力的な差別扇動が公然化し、インターネット上の人権侵害も広がっている。さらに、朝鮮学校や幼稚園の無償化排除反対のとりくみ、日朝国交正常化や「慰安婦」問題の解決など、日朝、日韓友好連帯活動や日中友好運動にも積極的にとりくむ必要がある。また、沖縄・辺野古の米軍新基地建設の強行は沖縄だけの問題ではなく、日本社会における差別構造の問題であることをしっかりと捉え、反戦・平和に向けた共同闘争として積極的にすすめていこう。
私たちはこうした厳しい情勢にたいして、社会連帯の闘いをすすめていかなければならない。
3月11日に、60年以上も無実を訴え続けてきた石川一雄さんが急逝した。石川一雄さんの遺志を受け継ぎ、第4次再審勝利をかちとるために、石川早智子さん、弁護団、共闘団体や住民の会とともに、全力で闘いをすすめなければならない。
5月17、18日に鳥取県鳥取市でひらく第68回全国女性集会での実践交流、討議の成果を活かし、部落解放運動だけではなく、さまざまな差別と闘う国内外の女性たちと反差別・反貧困のネットワークをつくることが求められている。
女性をとりまく情況は大きく変化してきている。女性差別をはじめあらゆる差別を許さず、ジェンダーによって役割を強制されたり、生き方を制限されたりすることのない社会の実現に向けて、部落女性の力を総結集して、第68回全国女性集会を成功させよう。
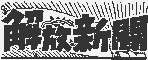
「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)