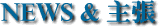
![]()
「解放新聞」(2025.08.15-3147)
1945年8月15日、日本の敗戦が決まった。
第2次世界大戦で、日本はアジア太平洋地域に侵略戦争を拡大し、多くの国や人々に計り知れない苦しみと被害をもたらした。中国や朝鮮半島、東南アジア諸国などでの軍事行動や植民地支配、民間人への被害、強制労働や従軍慰安婦問題など、過去の行為にたいする深い反省が求められている。私たちは、戦争によって失われた数多くの命と奪われた人権に思いを馳せ、同じ過ちを二度とくり返さないという強い誓いを新たにしていかなければならない。この80年の節目にあたり、日本がなすべきは過去の歴史と真摯に向き合い、戦争に反対し、平和憲法の理念を守り抜くことだ。戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継ぎ、差別や排外主義に抗いながら、平和とすべての人々の人権と尊厳を守る社会を築くために闘い続けていこう。
現在、ロシア・ウクライナ戦争の終結の見通しが得られないまま、イスラエルとハマスの戦闘も悪化の一途をたどり、イスラエルとイランの戦争も勃発した。現在もなお、子どもたちを含む多くの人々が犠牲になっている。まさに、世界の分断が勢いを増しながら進行しているようである。最大の懸念は、台湾有事と結びつくことで、戦争がいっそう拡大していくことだといわれている。中国の軍事的台頭を理由に、日本、とりわけ沖縄を中心とする南西諸島では安全保障上の緊迫度が増しているとして、防衛費の増額を求める声も強くなっている。
2012年末からの第2次安倍政権は7年8か月続き、「アベノミクス」とよばれる経済政策では、異次元の金融緩和による株価上昇や円安で、資産を持つ富裕層に恩恵をもたらした一方で、実質賃金が伸び悩み格差を拡大させた。また、15年9月に強行採決によって成立した「安全保障関連法」(「戦争法」)では、集団的自衛権の行使を可能とし、自衛隊の海外活動範囲の拡大が盛り込まれた。こうして日本の安全保障政策が「戦争ができる国」へと向かい始めた。22年12月にはこの方針を引き継いだ岸田首相が、反撃能力として敵基地攻撃能力の保有や弾薬・誘導弾などの継続戦力の確保が明記された安保関連3文書を閣議決定した。また、石垣島など南西諸島では、防空ミサイルや地対艦ミサイルの配備がすすめられている。そして防衛費は増加を続け、今年度は過去最大の8兆7005億円を計上している。軍拡路線は、戦争の惨禍を体験した国として歩むべき平和への道と相反するものであり、国際的な緊張を高める危険性すらはらんでいる。日本が本当にめざすべきは、武力を背景とした対立や抑止ではなく、対話と協調にもとづく信頼醸成と平和構築だ。
「戦争は最大の差別であり、最大の人権侵害である」という松本治一郎・元委員長の遺訓と戦前の歴史的教訓をふまえ、連帯・共闘する仲間とともに、各地から戦争と軍拡政策反対の声をあげ、命と暮らしを守り、平和と人権が確立した社会の実現にこそ力を注ぐべきだと強く訴えていかなければならない。
軍拡の影で、社会の分断や人々の不安もまた深まっている。トランプ米大統領は「自国第一主義」を掲げ、移民排斥やマイノリティ排除を声高に訴えている。その影響は世界にもおよび、経済的不安や社会的分断だけでなく、平和や人権をおびやかす空気が広がりを見せている。差別や排外的な言動が強まる状況は、けっして見過ごすことはできない。こうした流れは、戦争の記憶が薄れ世代交代がすすむ現代だからこそ、より慎重に警戒しなければならない課題だ。歴史に学ばず、対立や排除を正当化する言説が社会に広がれば、やがて誰もが安心して暮らせなくなる土壌を生む。だからこそ、いまこそ平和の価値や共生の理念を守り抜き、多様な人々が認め合い支え合える社会づくりに力を尽くすことが求められている。
社会の分断や排外主義の台頭は、たんなる政治的な現象にとどまらず、日常生活や地域社会にまで影響をおよぼしはじめている。SNSをはじめとした情報空間では、あやまった情報や偏見が拡散されやすく、感情的な対立や敵意が増幅されている。こうした流れのなかで、多様な価値観や文化をもつ人々がたがいに尊重し合い、ともに生きる社会の実現がかつてないほど問われている。いま私たちに必要なのは、不安や恐怖に根差した排除や対立ではなく、対話と理解を土台にした連帯の力だ。歴史的な過ちをくり返さないためにも、他者の痛みに心を寄せ、異なる声に耳を傾けることが求められている。こうした態度こそが、憲法が掲げる「平和主義」と「人権の尊重」を現実の社会に根付かせる第一歩となる。武力によらない紛争解決の道を追求し、国際的な課題にたいしても対話と協力をもってのぞむ姿勢を堅持することが求められている。だれもが安心して暮らせる未来のために、平和の礎を揺るがすいかなる動きにたいしても、私たちは声をあげ続ける必要がある。いまあらためて、平和の意義と人権の尊さを社会全体で再確認し、次世代に希望を手渡すための行動を積み重ねていこう。
2024年のノーベル平和賞を日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会が受賞した。ノーベル賞選考委員会は、「今年のノーベル平和賞を日本被団協に授与することで、肉体的な苦痛やつらい記憶にもかかわらず、大きな犠牲をともなう経験を平和への希望に捧げてきたすべての被爆者をたたえたい。いつの日か、被爆者が存在しなくなるときが来るだろう。しかし、記憶をとどめる継続的なとりくみによって、日本の新しい世代は被爆者たちの経験とメッセージを継承している。彼らは世界中の人たちを鼓舞し、伝え続けている。彼らは核兵器をタブーにするという、人類の平和な未来に不可欠な条件を維持することに貢献している」と、日本被団協や被爆者たちの活動を受け継ぐ意義を強調した。被爆者の証言に耳を傾けること、戦争の現実を直視し続けることは、私たちの責任であり、歴史の記憶を風化させてはならない。社会が分断や排外主義に傾く時代だからこそ、勇気をもって、争いではなく対話による解決をしていく姿勢が求められている。平和とは、たんなる「戦争がない状態」ではなく、誰もが人間らしく生き、たがいを尊重しあえる環境をつくる不断の努力の上に成り立つ。戦争を語り継ぎ、苦しみや悲しみから目を逸(そ)らさずに未来の世代へ手渡すことが、平和な社会の礎となる。
敗戦から80年、日本は着実に「戦争ができる国」へと向かっている。いまこそ、「平和主義」(憲法9条)「基本的人権の尊重」(憲法11条)「個人の尊厳」(憲法13条)「生存権」(憲法25条)が守られるよう、平和と人権、民主主義と共生など、日本国憲法の理念に立ち返るべきときである。
平和フォーラムが主催する、戦争犠牲者追悼、平和を誓う8・15集会が千鳥ヶ淵戦没者墓苑でひらかれる。満州事変から日中戦争、太平洋戦争へと拡大した戦争は15年にもおよんだ。政府によると、日本の戦没者は軍人・軍属230万人、民間人80万人が亡くなったとされている。また、アジア・欧米諸国にも多くの犠牲をもたらした。戦後生まれが人口の8割超を占め世代交代がすすむなか、戦争の悲惨さ、平和であることの大切さに次世代が真剣に向き合い、どう継承していくかが大きな課題だ。
私たちは、「戦争をさせない1000人委員会」や「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」に積極的に参加し、核と戦争のない平和な21世紀を実現しなければならない。そしてすべての市民と連帯・共闘し、「戦争法」廃止、平和憲法改悪阻止に向け全力でとりくもう。
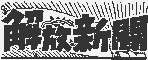
「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)