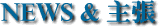
![]()
「解放新聞」(2025.10.05-3152)
2025年度部落解放・人権政策確立要求第2次中央集会を10月30日、東京・日本教育会館でひらく。今年4月1日に施行された「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称=「情報流通プラットフォーム対処法」。以下、「情プラ法」)の趣旨・目的などを、地方自治体と連携して周知徹底し、インターネット上の部落差別・人権侵害などをなくしていくとりくみを各地でもねばり強く展開していこう。
7月の参議院選挙で自民党が大敗し、衆参両院ともに少数与党という「異例の状況」を迎えた。10月4日に自民党の総裁選挙がおこなわれることから、中央集会がひらかれる頃には臨時国会がひらかれているものと思われる。連立政権構想などに注力するのではなく、長期化する物価高騰などが市民はもとより小規模・零細企業などを苦しめている現状を直視し、与野党一体での熟議による早期対策を強く望むものである。
「情プラ法」施行にともない、総務省は同法にもとづく措置を義務づける大手プラットフォーム事業者について、4月末にLINEヤフーやX(エックス)など5事業者、5月末にはドワンゴなど4事業者を指定した(以下、総称して「指定事業者」)。それぞれ3か月以内に「侵害情報調査専門員の選任」「情プラ法26条ガイドラインをふまえた削除基準の作成(改定)と公表」「誹謗中傷・権利侵害の削除申請窓口」などを整備し、総務省に届出をおこなう決まりだ。したがってすでにすべての指定事業者が届出を済ませ、9月から「情プラ法」に対応した削除申請窓口が本格的にスタートしたことになっている。中央本部でも、各指定事業者の削除申請窓口や削除手順などについて情報収集しているが、指定事業者ごとで実にさまざまだ。
「対応の迅速化」により、被害を受けた個人が「情プラ法」にもとづき削除を申し出た場合、指定事業者は7日以内になんらかの措置とその理由を通知すること、「運用状況の透明化」で指定事業者は「情プラ法」にもとづく削除などの運用状況を年度末に公表すること、となっている。あくまで指定事業者による自主規制のとりくみではあるが、これらの利点を最大限活かすことが重要である。中央本部・各都府県連で情報を共有化しながら、「情プラ法」にもとづく削除要請のとりくみを積極的に推進、強化していく。
一方、地方自治体で、人権に関する条例が20都府県、部落差別に関する条例が8府県、インターネット上の誹謗中傷等に関する条例が2府県で制定されている(2025年7月1日現在・地方自治研究機構調べ)。なかでも、21年以降に11府県(鳥取・鹿児島・宮崎・大分・秋田・愛知・三重・佐賀・山梨・沖縄・京都)で人権条例が制定・改正されていることに注目したい。個別人権課題の立法措置がはかられてきたことの影響もあるが、差別禁止などの規定が盛り込まれている条例も登場している。LGBTQ+にたいする差別やコロナ禍にともなう感染症患者等にたいする差別、野放し状態のネット上での部落差別や人権侵害など社会情勢が変化するなかで新たな人権課題に対応しようという機運が高まりをみせているといえる。「情プラ法」本格施行を機に、ネット上の被差別部落の所在地情報(識別情報の摘示)や人権侵害情報の削除が積極的におこなわれるよう、地方自治体にも働きかけて「情プラ法」にもとづく削除要請のとりくみを推進し、ネット上の人権侵害などの禁止を位置づけた「人権条例」等の制定・改定をめざしていこう。
近年、「識別情報の摘示」の動画などに関しては「地区内を巡回して、ようすを撮影した」ように見せかけ、被差別部落にたいする偏見・マイナスイメージなどを助長・拡散させるなど陰湿・巧妙化してきている。7月の法務省交渉で、法務省は2022~24年度の3年間での削除率は64%と回答した。しかし、削除されなかった残りの36%に「一般的に見て違法性が認められない識別情報」も含まれると思われる。私たちは断固としてネット上の「識別情報の摘示」をなくす闘いを強めていくことが必要である。くり返しになるが、被害を受けた個人が「情プラ法」にもとづく削除要請をおこなうことができる。摘示情報が流布された地域の住民などが削除を申し出ることがもっとも望ましいが、当事者の家族や本人から信託を受けた代理人、当該自治体からの削除要請のとりくみも追求しよう。他方、地方自治体などを通じた地方法務局への削除要請も連動させ、「情プラ法26条ガイドライン」をふまえて「識別情報により、当該地域で暮らす住民の「私生活の平穏」が脅かされている」ことを訴え、当該の自治体とも連携し削除要請にとりくんでいこう。
こうした削除要請をより推進していくためには、草の根レベルまで「情プラ法」の趣旨・目的などに関する理解と認識を広げ、深めていくとりくみや、被害を受けた人々を救済・支援する体制の整備がなによりも重要だ。6月に閣議決定された政府「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」(以下「第二次基本計画」)を具体化していくとりくみも推進・強化していこう。
「基本計画」の一部変更(2011年)から14年ぶりに改定された「第二次基本計画」は、インターネット上の人権侵害について課題横断的な人権課題にたいするとりくみとして項目立てがおこなわれた。ネット上で人権侵害などの被害者にも加害者にもならないためのとりくみや、あらゆる世代にたいするインターネットリテラシーの向上をはかるとりくみ、学校現場での「情報モラル」育成などである。
学校教育や社会教育、生涯教育(消費者教育を含む)を視野に入れた教育の充実、行政や携帯電話などを販売する事業者等を中心に、事業者とも連携した周知・啓発機会の拡充など「情プラ法」の趣旨・目的の普及啓発とあわせてとりくみを強めよう。なかでも、あらゆる世代にたいするインターネットリテラシー向上に関しては、地域レベルの「よろず相談(総合生活相談)」も救済・支援の担い手として位置づけていくことが重要である。「人権教育および人権啓発の推進に関する法律」にもとづいた「第二次基本計画」をふまえて、自治体レベルでも「人権教育・啓発基本計画」などの改定に向けて働きかけを強めよう。
東京都議会議員選挙につづき、参議院選挙でもSNS上で膨大な数の投稿が拡散し、多くの有権者の投票行動に影響を与えたといわれている。そのなかにはデマや偽・誤情報、ヘイト投稿も横行した。「情プラ法」は権利侵害などの情報にたいする指定事業者に自主的なとりくみを義務づけて促すものである。しかし、これら偽・誤情報やデマは、社会的・経済的マイノリティなどにたいする偏見や差別をさらに助長・扇動することにつながっている。こうした偽・誤情報も含めた対策では、プラットフォーム事業者の自主規制などにゆだねるのではなく、政府および地方自治体、業界をはじめ民間企業・団体などが力をあわせてとりくむことができるよう法制度の整備をはかっていくことが強く望まれる。「包括的な差別禁止法」と「国内人権機関の整備」が私たちのめざすところである。政局に振り回されることなく、官民一体で「情プラ法」に対応した削除要請の運動を展開しよう。ネット上の部落差別の削除へねばり強くとりくんでいくことをとおして、削除されなかった事案などをもとに法制度改正の根拠となる立法事実を積みあげていこう。
中央本部は、自民党「差別問題に関する特命委員会」や公明党「同和対策等人権問題委員会」、立憲民主党「人権政策推進議員連盟」などの院内活動や政府などへの働きかけを強化する。中央・地方レベルのとりくみから「情プラ法」成立時、衆参附帯決議に盛り込まれた第三者機関の整備など、法制度の充実を求める運動へとつなげていこう。
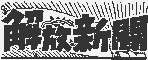
「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)